最近SNSを中心に話題の江戸時代の人の走り方「ナンバ走り」
見た目が面白くて奇妙な走り方なだけに、嘘でしょ?と思ってしまいます。
そんなナンバ走りは本当にあったのか?あったならなぜ消えてしまったのかを調査してみました。
「ナンバ走り」は本当か嘘か?
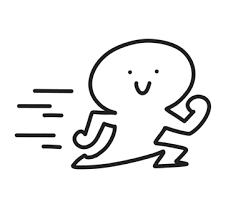
調査の結果、ナンバ走りは「本当」ですが、一部誇張された側面もあるというのが現在の専門家の見解です。
SNSでブレイクしたのは半身走り
📜 歴史的根拠
- 文献的証拠:1771年(明和8年)の『千里善走法』には「一日に四十里(約160キロ)を行くことあり」という記録が存在
- 浮世絵の描写:江戸時代の浮世絵には、腕を振らず上体を前傾させて歩く姿が描かれている Wikipedia
- 飛脚の存在:実際に長距離を人力で移動する職業があり、効率的な走法が必要だった
🤔 疑問視される点
- 明治初期の動画では確認されるが、大正時代にはほとんど見られなくなる
- 幕末期の訪日外国人の見聞録にナンバ歩きの明確な記述が皆無 Wikipedia
- 現代の時代劇でも俳優は通常の歩き方をしており、刀と着物でもナンバでない歩行が可能
ナンバ走りのやり方
🏃♂️ 基本的な技術
正しいナンバ走りの特徴
- 体を捻らない:右手と右足、左手と左足を同時に動かすのではなく、肩が上下に動く
- 膝を軽く曲げ、つま先を体の真下に着地
- 地面を「蹴る」のではなく「引き抜く」ように足を上げる
- 肘から先を上下に動かすイメージで腕を使う
- 呼吸は鼻で静かに、リズムを一定に保つ
練習方法
- 歩きから始める:まずナンバ歩きをマスターする
- 腕の動き:前後に振らず、体の横で肘から先を上下に動かす
- 段階的移行:軽いジョギングからナンバ走りのフォームを意識
- 地面との接触:足が着地するタイミングと肩の動きを同調させる
メリットとデメリット
✅ メリット
エネルギー効率の向上
- 体の捻りがないため、エネルギーロスが少ない
- 内臓が捻られないため呼吸がしやすく、スタミナが消耗されにくい
- 長距離でも疲れにくいと多くの実践者が報告
身体への負担軽減
- 関節への負担が減る
- 体幹が安定し、バランス感覚が向上
- 腰痛の軽減効果も報告されている
効率的な推進力
- 地面を効率よく蹴ることができる NARUTO公式
- 上体のブレが少なく、前進力を効率的に活用できる
❌ デメリット
適用範囲の限界
- 高速走行時には不向き:インターバルトレーニングや全力疾走では従来の走法の方が速い場合がある
- 階段ダッシュなどでは腕を振った方が効率的との報告も
習得の困難さ
- 現代人には不自然な動作で習得に時間がかかる
- 正しいフォームの確立が困難
- 間違った理解での実践では効果が得られない
科学的検証の不足
- 感覚的な説明が多く、客観的データが限られている
- 個人差が大きく、万人に有効とは限らない
なぜ消えた?明治時代の西洋化
🏛️ 消失の主な理由
1. 西洋式軍事訓練の導入
- 明治政府が西洋式軍隊の行進を採用
- 軍事教練を通じて現代的な歩行・走行法が普及
- 学校教育でも西洋式の体操が奨励された
2. 生活様式の変化
- 洋服の普及により、着物に適したナンバ歩きが不要に
- 舗装道路とシューズの普及で、従来の草鞋での移動技術が不要に
- 交通手段の発達で長距離徒歩移動の必要性が減少
3. 文化的価値観の転換
- 「文明開化」の名の下での西洋化推進
- 従来の日本的な身体技法が「遅れたもの」として認識される風潮
- 「進歩」の象徴として西洋式の動作が重視
📊 消失の時期
- 明治初期(1870年代):軍事訓練を通じた西洋式歩行の導入
- 明治中期(1880-1890年代):学校教育での体操普及
- 大正時代(1910年代以降):一般市民からナンバ歩きがほぼ消失
現代での再評価
🔬 スポーツ科学の視点
元オリンピック選手の為末大氏は、ナンバ走りについて以下のように分析しています:
- 「ねじれない走り」が本質:肩と腰の2つの軸が固定された状態で走る技術
- 魔法の技術ではない:劇的な効果を期待するのは現実的でない
- 複合的アプローチが必要:ナンバ走りだけでなく、様々な技術の組み合わせが重要
🌟 現代での応用
ランニング愛好家での活用:
- マラソンなどの長距離走での疲労軽減効果
- 体への負担を減らしたいランナーに人気
- リハビリテーションでの応用も検討されている
武道・スポーツでの応用
- 古武術の身体操法として継承
- 体幹トレーニングの一環として活用
- バランス感覚の向上に効果的
結論:事実と推測の境界線
ナンバ走りの真実
- ✅ 江戸時代に効率的な移動技術が存在したことは文献的に確認できる
- ✅ 現代でも長距離走で効果を実感する人がいることは事実
- ❓ 当時の一般的な走法だったかどうかは完全には立証されていない
- ❓ 現代に完全復元されたとは断言できない
ナンバ走りは「江戸時代の断片的事実を現代に再構成した身体技法」として理解するのが適切でしょう。完全な歴史的復元というより、効率的な身体の使い方を追求する現代の取り組みとして評価するのが妥当です。
参考文献・動画



コメント